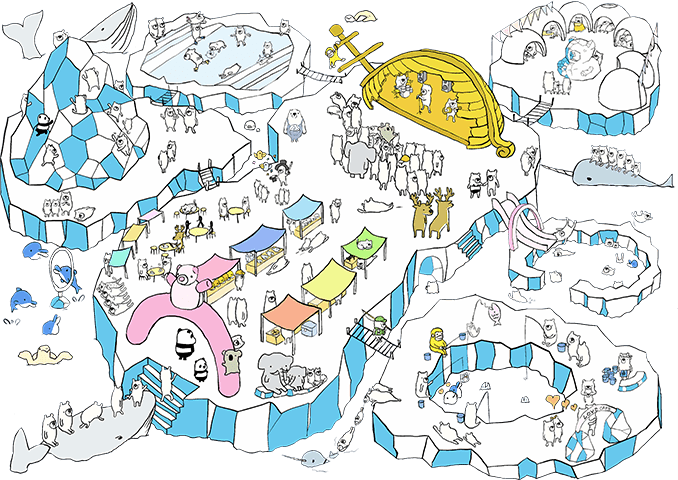ZEB(ゼブ)とは?種類ごとの定義や評価基準、実例をわかりやすく解説
公共施設や工場など、非住宅で排出するCO2の削減を目指すZEB(ゼブ)。
国が宣言した「2050年のカーボンニュートラルの実現」をかなえる手段として、注目が集まっています。
この記事ではZEBの定義や評価基準など、ZEBの基礎知識を詳しく解説します。
実際にZEB化した建築物の事例も紹介するので、ZEBを検討する際の参考にしてください。
ZEBとは
引用:環境省ZEB PORTAL「ZEBとは?」
ZEB(ゼブ)とは、建築物で使う年間の一次エネルギーを実質ゼロにするのを目指した建築物で、ネット・ゼロ・エネルギー・ビルの略称です。
建築物の省エネ性能や断熱性能を向上させてエネルギー消費を減らし、活動するためにどうしても消費しなければいけないエネルギーを自分たちで作ることで、エネルギー収支をゼロにします。
ZEB化に必要な3つの技術
建築物をZEB化するには、「パッシブ技術」「アクティブ技術」「創エネ技術」の3つが有効です。
引用:環境省ZEB PORTAL「どうやったらZEBがつくれるの?」
まず外皮性能の向上や日射遮蔽などで室外の熱が室内に入るのを抑え、できる限り冷暖房を使わなくても室内環境を快適に維持できる設計にします。
次に室内で活動する上で欠かせないエネルギーを無駄なく使用するために、高効率空調など省エネ性能の高い設備を導入します。
そして使用するエネルギーを、太陽光発電やバイオマス発電などで生成することで、建築物で消費するエネルギーの正味ゼロがかなう、という流れです。
ZEBのランクごとの定義と評価基準
ZEB化の実現には大幅な省エネと大量の創エネが必要であり、導入ハードルが高いのが難点です。
そこで建築物の規模や実情に合わせ、4つのランクが設けられています。
引用:環境省ZEB PORTAL「ゼロエネルギー化って本当にできるの?」
エネルギー削減率0%以下が難しい場合でも、無理なく導入できるランクを選ぶことで、積極的にZEB化を取り入れていく姿勢が重要です。
非住宅をZEB化する流れ
建築物をZEB化するには、新築で2年程度、既存建築物の改修で2〜3年程度かかるとされています。ZEB化には専門的な知識や技術が求められるため、建築計画の段階から専門家との協議が必要です。
環境省が想定する新築建築物のZEB化の流れは、下記のとおりです。
①ZEB設計を依頼する事業者の選定
②事業者によるZEB設計
③BELS評価によるZEBの証明
④ZEB補助事業の申請(補助金等を利用する場合)
⑤施工業者の決定
⑥施工
⑦施工検査
⑧補助事業の実績報告書を提出
補助事業を利用する場合は年度初めに申請する必要があるため、前年度に設計や証明を済ませるのがポイントです。
非住宅をZEB化する4つのメリット
ZEB化した建築物を所有している企業が、得られるメリットを4つ解説します。
光熱費を削減できる
エネルギー消費量の削減率と比例して、光熱費も抑えられるのがZEB化の大きなメリットです。
環境省によると、延床面積10,000㎡程度の事務所ビルや、延べ床面積3,000㎡程度のスーパーマーケットで消費エネルギーを50%削減できた場合、年間の光熱費は40〜50%程度削減できると試算されています。
参考:環境省「建築物のZEB化推進に向けた取り組み」
さらに創エネシステムでエネルギーを生成できれば、より大きく光熱費を削減できるでしょう。
快適性や生産性が向上する
断熱性能が高く一年中快適な室温を保ちやすいため、建築物内で働く人の作業効率が上がり、生産性の向上が期待できます。
熱中症やヒートショックなどの健康リスクも軽減してくれるので、テナントを利用する人や従業員の健康を守るために大切な役割を果たしてくれるでしょう。
企業の信頼性や不動産価値が高まる
近年、世界中で「持続可能な社会づくり」が促進されており、環境・社会・ガバナンスの観点から持続可能な会社を目指すESG経営に注目が集まっています。
環境に配慮したZEB建築を持つ企業はESG経営だと認められ、信頼性やブランドイメージの向上がかなうでしょう。
また、ZEB化したビルのテナントも、借りた企業がESG経営をアピールできるため需要があり、一般的なテナントよりも高い賃料に設定できます。
災害時でも事業継続性を維持できる
地震など自然災害が発生した際、事業を継続できなくなる理由の多くは停電が原因です。
引用:環境省「建築物のZEB化推進に向けた取り組み」
建築物でエネルギーを生成できるZEBは、停電中でも電力を使用できる可能性が高いため、事業を継続できる可能性が高いのがメリットです。
災害時の復旧を支援する場所としても活躍できるので、地域貢献にもつながります。
非住宅をZEB化する際の注意点
ZEB化には専門的な知識や技術が必要なうえ、エネルギー消費量を実質ゼロにするという非常に厳しい条件があるので、実際の建築物が出来上がるまで時間やコストがかかるのが難点です。
ZEB化を希望する場合は、早い段階から専門家と協議を行うのが重要です。
また高度な省エネ設備などを導入するため、一般的な建築物よりも初期コストが高くなるのは避けられません。初期コストをできるだけ抑えるには、ZEB化を支援する補助金制度を上手く活用しましょう。
【2025年度】ZEB化に利用できる補助金制度2選
2025年度に使える補助金制度を2つ解説します。
新築建築物のZEB普及促進支援事業/既存建築物のZEB化普及促進支援事業
新築建築物のZEB普及促進支援事業/既存建築物のZEB化普及促進支援事業は、業務用建築物のZEB化普及拡大を目的とした制度です。
公募期間は令和7年6月10日〜7月18日で、ZEBリーディング・オーナーへの登録とZEBプランナーの関与が必須要件です。
補助対象への交付金の補助率は、下記の通りです。
| ZEBランク | 新築建築物 | 既存建築物 | ||||
| 2,000㎡未満 | 2,000㎡~10,000㎡ | 10,000㎡以上(地方公共団体のみ) | 2,000㎡未満 | 2,000㎡~10,000㎡(地方公共団体のみ) | 10,000㎡以上(地方公共団体のみ) | |
| ZEB | 2分の1 | 2分の1 | 2分の1 | 3分の2 | 3分の2 | 3分の2 |
| Nearly ZEB | 3分の1 | 3分の1 | 3分の1 | 2分の1 | 3分の2 | 3分の2 |
| ZEB Ready | – | 4分の1 | 4分の1 | – | 3分の2 | 3分の2 |
| ZEB Oriented | – | – | 4分の1 | – | – | 2分の1 |
交付の上限は、すべて3億円までと定められています。
LCCO2削減型の先導的な新築ZEB支援事業
LCCO2削減型の先導的な新築ZEB支援事業は、建築物の運用時のみだけでなく、建築時や廃棄時など建築物のライフサイクルを通じて生じるCO2の削減を目指す建築物を支援する制度です。
公募期間は令和7年6月10日〜7月18日で、ZEBリーディング・オーナーへの登録とZEBプランナーの関与が必須要件です。
補助対象への交付金の補助率は、下記の通りです。
| ZEBランク | 補助率(上限5億円) |
| ZEB | 5分の3 |
| Nearly ZEB | 2分の1 |
| ZEB Ready | 3分の1 |
| ZEB Oriented | 3分の1 |
車載型蓄電池や充放電設備などを導入した場合も、それぞれ補助金を受けられます。
実際にZEBを導入した建築物の事例
実際にZEB化が成功した建築物の事例を3つ選び、表にまとめました。
成功ポイントも記載するので、ZEB化を検討する際の参考にしてください。
| 団体名 | ランク | 用途 | 一次エネルギー削減率(創エネ除く/含む) | 成功ポイント |
| 日本地下水開発株式会社 | ZEB | 事務所 | 58%/100% | ・地下帯水層を蓄熱槽として活用したトータル熱供給システム・断熱による冷暖房エネルギーの削減 |
| 東京都品川区 | Nearly ZEB | 集会所 | 58%/91% | ・深い庇やLow-Eガラスで高遮熱と断熱化・高効率空冷ヒートポンプチラーと地中熱ヒートポンプチラーによる省エネ |
| 昭和興業株式会社 | ZEB Oriented | テナントビル | 65%/105% | ・高効率空調、LED照明システム、CO2センサー付き換気システム等の採用 |
ZEB化でよくある質問3選
ここでは、建築物のZEB化でよくある質問を3つ解説します。
ZEHとZEBの違いは?
ZEHとは、断熱性能と省エネ性能を向上させ、使用するエネルギーを創エネすることで、建築物で使用するエネルギーの収支ゼロを目指すものです。
ZEBの目指す目標と同じですが、ZEBが公共施設や工場など非住宅を対象にしているのに対し、ZEHは住宅が対象です。
2030年までにZEB水準の省エネ性能が義務化する?
引用:環境省ZEB PORTAL「ZEB普及目標とロードマップ」
国土交通省の「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針の改正案について」によると、中大規模建築物の誘導基準への適合率が8割以上、遅くても2030年までには省エネ基準をZEB水準に引き上げることが検討されています。
今後省エネ基準がZEB水準になる可能性は高いので、今からZEB水準に対応していく姿勢が重要です。
ZEB化にかかる費用は?費用対効果はある?
ZEB化にかかる費用は建築物の規模等で異なりますが、環境省によるとオフィスビルをZEB Ready化した場合、一般的な建築物と比較して10%程度コストが増えると試算しています。
参照:環境省「建築物のZEB化推進に向けた取り組み」
ZEB Readyは年間のエネルギー消費量を50%以上削減できる見込みなので、光熱費も同程度の削減が期待でき、長い目で見れば費用対効果があるといえるでしょう。
まとめ
地球環境を守りながら快適な暮らしを手に入れていくには、ZEBやZEHなど建築物で消費するエネルギーを削減する省エネ建築物の普及が不可欠です。
ZEB水準の省エネ性能が基準になる時代に近づいているので、建築事業者は建築主にZEB化をすすめていく姿勢が大切です。
省エネ計算なら、しろくま省エネセンターにお任せください!
しろくま省エネセンターでは、業界初の「省エネ計算返金保証」を行っております。
個人住宅、小規模事務所から大型工場などまで、幅広く対応しています。まずはお気軽にご相談ください!