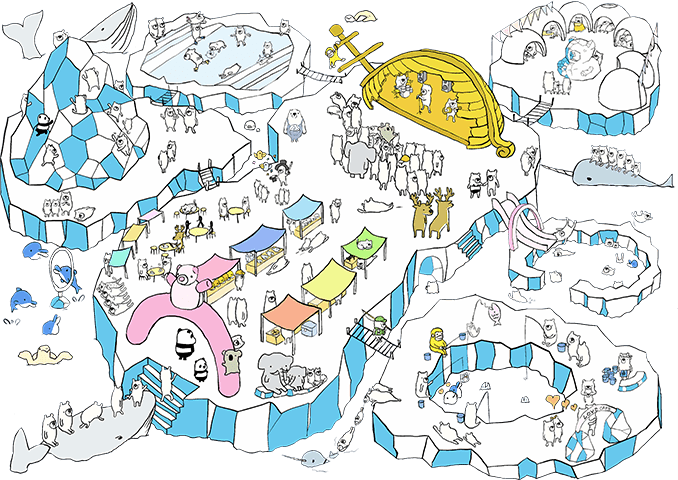住宅性能表示とは?制度のメリットから評価項目までわかりやすく解説
住宅性能表示制度は、建築物の性能を客観的に評価・表示する仕組みです。
この制度を活用することで、建築主は住宅の品質を正確に把握でき、設計者は自身の技術力をアピールできます。
この記事では、制度の基本から具体的な評価項目、活用方法まで、わかりやすく解説していきます。
住宅性能表示とは
住宅性能表示制度は、建築物の性能を第三者機関が客観的に評価する国の制度です。
耐震性や省エネ性能、維持管理のしやすさなど、住宅のさまざまな性能を共通の物差しで評価し、わかりやすく表示できます。
住宅性能表示制度の仕組み
この制度は、住宅の性能を決められた基準で評価し、わかりやすく表示する仕組みです。
評価は国土交通大臣に登録された第三者機関が行うため、公平で信頼性の高い結果が得られます。
評価を受けるには、設計段階と建設段階の2回の審査が必要です。
設計段階では図面などをもとに評価を行い、建設段階では実際の建物を確認して最終的な評価を決定します。
性能の評価結果は「住宅性能評価書」として発行され、わかりやすくまとめられているため、専門知識がない方でも理解しやすい形になっています。
引用:設計住宅性能評価書のイメージ (一戸建ての住宅の場合)
住宅性能表示と住宅性能評価の違いは?
住宅性能表示と住宅性能評価は、よく混同されがちな用語ですが、実は役割が異なります。住宅性能評価は、専門家が住宅の性能を具体的に調べて判定する作業のことを指します。
一方、住宅性能表示は、その評価結果をわかりやすく見える化したものです。つまり、住宅性能評価は「調べて判定する作業」、住宅性能表示は「結果を表示する方法」というように、それぞれ異なる役割を持っているのです。
新築住宅と既存住宅で異なる評価方法
新築住宅と既存住宅では、評価の方法や時期が大きく異なります。
新築住宅の場合は、設計図書をもとに行う設計住宅評価と、実際の建築物を確認する建設住宅評価の2段階で評価を行います。新築住宅はすべて同じ基準で評価するので、他の新築住宅と比較も可能です。
既存住宅の場合は、現地での建物調査が中心となります。
築年数や修繕の履歴、実際の劣化状況などを詳しく調べ、現在の性能を総合的に判断しなければなりません。
また、評価できる項目数も異なり、新築住宅では10項目をすべて評価します。
一方、既存住宅では建物の状態によって評価できない項目があります。
国土交通省が定める評価機関の役割
評価機関は、国土交通大臣の登録を受けた第三者機関です。
この機関には、公平で正確な評価を行うための厳格な基準が設けられています。
評価機関の主な役割は、設計図書の審査や現場での検査、評価書の発行などを行います。
特に重要なのは、どの評価機関で評価を受けても同じ基準で判断される点です。
評価機関を選ぶ際は、対応地域や評価料金、評価までにかかる期間なども確認してください。事前相談にも応じてくれる機関が多いため、不明な点があればぜひ問い合わせてみましょう。
住宅性能表示制度の10項目とは?
住宅性能表示制度では、住宅の性能をさまざまな観点から総合的に評価します。
評価項目は全部で10項目あり、このうち4項目 は必ず評価を受けなければなりません。
これらの項目は、住まいの安全性や快適性に直接関わる重要な要素です。
それぞれの項目について、具体的に見ていきましょう。
1. 構造の安定性について
構造の安定性は、住宅の安全性を左右する最も基本的な性能です。
地震や台風、積雪などの自然災害に対する強さを評価します。
具体的には、建物の構造体の強度や地盤の安定性、基礎の仕様などをチェックしていきます。これは必須項目の一つであり、特に重要な評価ポイントです。
2. 火災時の安全性について
火災に対する安全性は、人命に関わる重要な項目です。
火災の発生を早期に発見できる設備や、火災が起きた際の避難のしやすさを評価します。
具体的には、火災警報器の設置状況や避難経路の確保、延焼を防ぐ対策などをチェックしていきます。
3. 劣化軽減について
劣化軽減対策は、建築物を長く使い続けるために欠かせない性能です。
木材の腐食やシロアリ被害を防ぐための対策やコンクリートの品質など、劣化の進行を遅らせるための対策を評価していきます。
これは必須項目の一つとなっており、建築物の寿命を左右する重要な要素です。
4. 維持管理・更新への配慮について
維持管理のしやすさも、必須項目の一つです。
給水管やガス管、排水管などの設備の点検や修理がしやすい構造になっているかを評価します。
将来的なメンテナンスコストにも関わる大切な項目です。
5. 温熱環境・エネルギー消費量について
断熱は、快適な室内環境を作るための必須項目です。
壁や天井、床の断熱性能や、窓の気密性などを評価します。
「外皮(外壁、窓など)の断熱等性能」と「一次エネルギー消費量」の2つを表示します。
6. 空気環境について
室内の空気環境は、健康に直接関わる重要な要素です。
換気設備の性能や、建材から発生する化学物質への対策を評価していきます。
特に小さな子どもやお年寄りがいる家庭では、重要な検討項目です。
7. 光・視環境について
採光や景観は、日々の暮らしの質に関わる要素です。
居室の開口部の面積と位置についての配慮を評価します。
窓の大きさなどの配置によって、部屋の明るさなどが変わり、生活の質に関わる項目です。
8. 音環境について
防音性能は、特に都市部での生活の質を左右する重要な要素です。
外部からの騒音を防ぐ性能や、室内での音の響き方を評価します。
住宅の立地条件によっては、特に重視すべき項目となるかもしれません。
9. 高齢者等への配慮について
バリアフリー性能は、将来を見据えた重要な要素です。
段差の解消や手すりの設置など、高齢者や障害者の方にも使いやすい設計かどうかを評価していきます。
家族構成や将来の生活スタイルを考慮して、検討する必要があるでしょう。
10. 防犯について
防犯は、住まいの安心感に直結する要素です。
玄関や窓の錠前の性能など、「被害対象の強化」に着目して、住宅の開口部における侵入防止対策、防犯に関する設備を評価します。
「監視性の確保」「領域性の強化」「接近の制御」「被害対象の強化」という4つの原則を守ることが有効です。
住宅性能表示の等級とは
住宅性能の評価結果は、項目ごとに等級という形で表示されます。
等級が高いほど、その項目の性能が優れていることを示しています。
この等級による表示方法は、専門知識がなくても性能の違いが一目でわかる特徴があります。
住宅性能は等級で表示される
住宅性能の等級は、項目によって1級から7級までの範囲で評価されます。
一般的に数字が大きいほど高性能を示しますが、項目によって基準となる等級が異なることもあります。
例えば、耐震性能の場合、等級1は建築基準法の最低基準を満たすレベル、等級3は最高レベルとなります。このように、項目の特性に応じて等級の幅や基準が設定されています。
項目別の等級基準
各評価項目の等級基準は、性能の種類によって細かく定められています。住宅の特徴や建築主の要望に応じて、重視する項目の等級を上げることで、より良い住まいづくりが可能となるでしょう。
| 評価項目 | 等級 |
| 構造の安定 | 等級1~3 |
| 火災時の安全 | 等級1~4 |
| 劣化の軽減 | 等級1~3 |
| 維持管理・更新への配慮 | 等級1~3 |
| 温熱環境(断熱性能) | 等級1~7 |
| 空気環境 | 等級1~3 |
| 光・視環境 | 開口率・開口比 |
| 音環境(遮音性能) | 等級1~5 |
| 高齢者等配慮(バリアフリー) | 等級1~5 |
| 防犯性能 | 階ごと |
また、必須項目については最低限クリアすべき等級が定められています。
この基準を満たした上で、建築主の優先順位に応じて各項目の等級を検討していくことが重要です。
住宅性能表示のメリット
住宅性能表示制度を活用することで、設計者と建築主の双方にさまざまな利点があります。
この制度を上手に活用することで、より良い住まいづくりと、スムーズなコミュニケーションが実現できるでしょう。
設計者・施工者のメリット
住宅性能表示制度は、設計や施工の品質を客観的に示す有効なツールです。
第三者機関による評価結果を示すことで、自社の技術力や提案内容を具体的な数値で証明できます。
また、評価書の内容を契約に含めることで、トラブルを未然に防ぐことも可能です。
性能が数値で明確に示されるため、建築主との認識のずれを防ぎ、安心して工事を進められるでしょう。
建築主・購入者のメリット
建築主にとって最大のメリットは、住宅の品質を客観的に判断できる点です。
性能が等級という形でわかりやすく示されるため、複数の住宅を比較検討する際の基準として活用できます。
また、評価書は住宅ローンの金利優遇や住宅保証の付帯条件としても活用できます。万が一のトラブル時には、専門の紛争処理機関を利用することもできるため、安心感が高まるでしょう。
まとめ
住宅性能表示制度は、良質な住まいづくりを支援する重要な仕組みです。しかし、評価項目や基準の詳細については、専門的な知識が必要となりますので専門業者さんにお問い合わせすることを推奨致します。
省エネ計算なら、しろくま省エネセンターにお任せください!
しろくま省エネセンターでは、業界初の「省エネ計算返金保証」を行っております。
個人住宅、小規模事務所から大型工場などまで、幅広く対応しています。まずはお気軽にご相談ください!