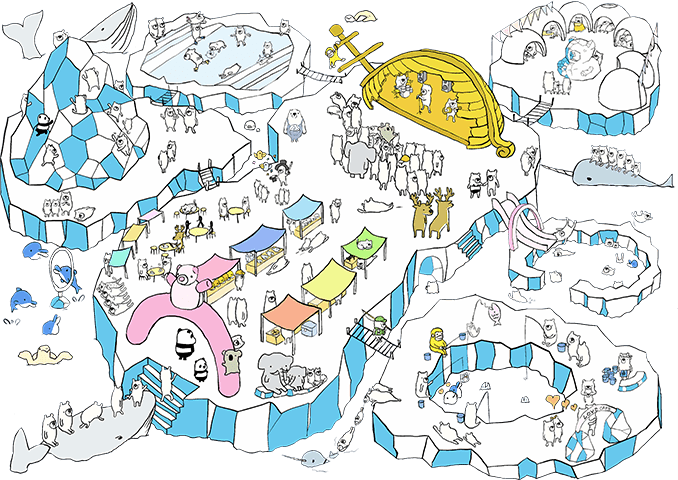サステナブル住宅とは?9つの性能やメリット、最新の補助金制度を解説
近年、環境問題対策のひとつとして、世界中でトレンドになっている「サステナブル」。
住宅業界でも、環境保全を目的とした「サステナブル住宅」の普及が促進されています。
この記事ではサステナブル住宅の概要やメリット、サステナブル住宅の条件に該当する住宅認定制度について解説します。
初期コストを抑える補助金制度も紹介するので、サステナブル住宅を検討する際の参考にしてください。
サステナブル住宅とは
サステナブルとは「持続可能な」という意味で、既存資源を大切に使い、環境を保全することで、将来にわたって持続可能な状態を維持する取り組みを指します。
一般社団法人日本建設業連合会では、「サステナブル建築」の概念を次のように示しています。
①建築のライフサイクルを通じて省エネ・省資源・リサイクル・有害物質排出の抑制を図る
②地域の気候や伝統、文化および周辺環境と調和する
③将来にわたって人間の生活の質を適度に維持・向上が期待できる
つまり、サステナブル住宅は、将来を見据えて地球環境・周辺環境・生活環境に配慮した、地球にも人にも優しい住宅ということです。
サステナブル住宅に必要な9つの性能
サステナブル住宅は概念であり、国や公共団体が定める明確な基準などはありません。
一般的にサステナブル住宅で必要とされている主な事項は、次の9つです。
| 視点 | 環境設計配慮事項 | 概要 |
| 地球環境 | 省エネ性 | 化石エネルギー消費が最小になる設計及び運用 |
| 創エネ性 | 創エネを活用できる設計及び運用 | |
| 耐久性 | 長く使い続けられる建築物の設計及び運用 | |
| ライフサイクル | 設計・施工・運用・改修・廃棄プロセスを通じ、一貫したライフサイクル・マネジメント | |
| 地域配慮 | 環境影響配慮 | 土壌汚染・大気汚染・水質汚染・騒音などへの配慮 |
| 都市のヒートアイランド抑制 | 外構・屋上・壁面の緑化、保水床・打水など | |
| 生活環境 | 健康性 | 化学汚染物質・感染症対策など |
| 快適性 | 温熱環境・光環境・音環境など | |
| 更新性 | 可変性・拡張性など |
他にも自然災害時の安全性や環境負荷の少ないリサイクル材の利用など、さまざまな環境配慮が求められます。
参照:一般社団法人日本建築業連合会「サステナブル建築を実現するための設計指針」
すべての項目を満たすのは非常に難しいので、無理なくできる項目を取り入れるのが大切です。
サステナブル住宅を実現させる6つのポイント
サステナブル住宅を実現させるのに、抑えたいポイントを6つ解説します。
高い断熱性能で一年中室内を快適に保つ
住宅で消費するエネルギーを削減するには、室外の熱が室内に伝わりにくくする断熱性能の高さが不可欠です。
断熱性能が高ければ、少ないエネルギーでも一年中快適な室温に保ちやすくなります。
太陽光などの再生可能エネルギーを使う
エネルギー消費を実質ゼロに近づけるには、必要なエネルギーを自然エネルギーで補う必要があります。
断熱性や省エネ性を高めたうえで、生活にどうしても必要なエネルギーを太陽光発電などで生成することで、CO2の削減だけでなく限りある資源の保全がかないます。
日射や自然風を活用するパッシブデザインを取り入れる
省エネ住宅には高性能な設備が必要ですが、機械には必ず故障や寿命があり、サステナブルとは言い難いのが欠点です。
そのため機械に頼りすぎずに快適な室内環境を整えるために、自然の力を利用した「パッシブデザイン」の設計がおすすめです。
例えば、冬の日射を室内に取り込む窓配置や、風通しを考慮した間取りなどがパッシブデザインの一例です。
停電時に冷暖房設備などが使用できなくなった際に自然の力が活用できるので、災害時でも生活を維持しやすいのも魅力です。
住宅の長寿命化につながる耐震性や耐久性を高くする
サステナブル住宅では住宅の運用時だけでなく、建築時や廃棄時のCO2を削減するために、ひとつの住宅に長く住み続けられる環境づくりが求められます。
地震や台風など自然災害が多い日本で住宅の寿命を長くするには、耐震性や耐久性の高さが絶対条件です。
地震や風による揺れに強い構造躯体にする、点検口を確保して維持管理を容易にするなど、長く良好な状態が維持できる設計に注力しましょう。
構造体に環境負荷の少ない木造建築を選ぶ
樹木はCO2を吸収する機能があり、住宅に使用されている木材は、炭素を固定した状態で保持しており、焼却などをしない限りCO₂として大気中に戻ることはありません。
そのため家づくりに木材を使用してまた新しい樹木を植えれば、大気中のCO2削減につながります。
引用:一般社団法人日本木造住宅産業協会「木造戸建て住宅の炭素貯蔵量」
また、木造住宅の材料を生成する際に排出されるCO2量が1だとすると、鉄骨造の材料生成は2倍程度、鉄筋コンクリート造は2.5倍程度多いといわれています。
木造住宅を選ぶだけで、地球温暖化防止への貢献が実現するでしょう。
参照:林野庁「令和6年度森林・林業白書」
ライフスタイルの変化でフレキシブルに対応できる間取りにする
「家族構成やライフスタイルが変わったから家を住み替える」ではなく、年月が経ってもひとつの住宅に長く住み続けられるよう、フレキシブルに対応できる間取りにするのもサステナブル住宅に必要な要素です。
年を重ねたあとのライフスタイルを考えて段差の少ない設計にするなど、何十年も先を見通したプランニングを行いましょう。
サステナブル住宅を選ぶメリット
サステナブル住宅は環境に優しいのはもちろん、住む人にとっての快適で健康的な生活を追求しています。
エネルギーの消費を抑えられるため光熱費も安くなり、家計に優しい点も魅力でしょう。
人と自然が無理なく共存していくうえで、必要な要素が詰まっているといえます。
サステナブル住宅を選ぶデメリット
サステナブル住宅を選ぶ際に注意したいのが初期コストの高さです。
省エネ性能の高いエアコンなど、高性能な設備を導入する必要があるため、一般的な住宅よりもコストがかかるのは避けられません。ただし、前述した通り、光熱費の削減が期待できるため、長期的に見ればコストパフォーマンスが高いといえます。
また、国や地方自治体が用意する補助金制度を活用して、初期コストを抑えるのも大切です。
サステナブル住宅を目指すのに適した認定制度3選
ここではサステナブル住宅の考えに該当する、主な住宅認定制度を3つ解説します。
ZEH住宅
ZEH住宅は住宅で使用するエネルギーを減らし、太陽光発電などで生成したエネルギーを使うことで、住宅で消費するエネルギーの実質ゼロを目指す住宅です。
引用:経済産業省資源エネルギー庁「ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」
サステナブル住宅の中でも、省エネ性能に特化した住宅を求める方に適した制度といえます。
長期優良住宅
長期優良住宅は、住宅を長く良好な状態で使い続けるための措置が講じられた優良な住宅です。
省エネ性能や断熱性能だけでなく、下記の措置を講じる必要があります。
①長く使うための構造や設備を有している
②居住環境などへの配慮がある
③一定面積以上の住戸面積がある
④維持保全の期間や方法を定めている
⑤自然災害への対策を行っている
引用:一般社団法人住宅性能評価・表示協会「長期優良住宅とは」
住宅の耐久性や可変性などの基準もあり、サステナブル住宅に必要な性能を多く備えています。
【2025年度】サステナブル住宅を支援する補助金制度
サステナブル住宅で補助金制度を活用するには、ZEHや長期優良住宅を取得するなど国が定める認定制度の基準を満たす必要があります。
サステナブル住宅を建てる際に使われる主な補助金制度は、次のとおりです。
| 制度 | 概要 | 補助金額 |
| 子育てグリーン住宅支援事業 | 子育て世帯や若者世帯をメインに省エネ住宅の獲得を支援 | GX志向型住宅:160万円/戸長期優良住宅:80万円/戸ZEH住宅:40万円/戸 |
| ZEH補助金 | ZEH住宅を建築・購入等する個人を対象に支援 | ZEH:55万円/戸ZEH+:90万円/戸 |
| サステナブル建築物等先導事業 | 先導性の高い省CO2対策を行っている住宅を支援 | ZEH水準:補助対象費用の1/2 |
※子育てグリーン住宅支援事業の新築・GX志向型住宅分は、補助金申請額が予算上限額に達したため、交付申請(予約含む)の受付を終了しています。
※詳細や最新情報は各HPにてご確認ください。
サステナブル住宅でよくある質問2選
サステナブル住宅でよくある質問を、2つ解説します。
サステナブル住宅の認定基準はある?
基本的にサステナブル住宅は概念なので、ZEH住宅や長期優良住宅のような国が定める認定基準はありません。
ただし、地方自治体や金融機関などが補助金や金利の引き下げなどをサポートする際に、独自の認定基準を設けている場合があります。
例えば四国銀行では、四国銀行が定めるサステナブル住宅認定基準に該当する住宅に対し、変動金利を0.1%引き下げるなどのサービスを実施しています。
参照:四国銀行「エコ住宅」
サステナブル住宅の事例は?
サステナブル住宅の事例を参考にするなら、IBECs(一般社団法人住宅・建築SDGs推進センター)が隔年で開催している「SDGs住宅賞」がおすすめです。
各作品ごとに設計者の情報や環境性能、サステナブル住宅を設計するコツなどが詳しく記載されています。
参照:IBECs「SDGs住宅賞」
まとめ
サステナブル住宅は、環境問題の要因であるCO2排出量を削減しつつ、人にとっても住みやすい居住環境づくりをかなえるのを目的にした住宅です。
持続可能な社会の実現のために、建築事業者は消費者へサステナブル住宅を積極的に普及していく姿勢が求められています。
ZEH住宅等の認定や補助金制度の利用には、難しい省エネ計算や図書作成等の手間がかかるので、申請の代行業者への外注をおすすめします。
省エネ計算なら、しろくま省エネセンターにお任せください!
しろくま省エネセンターでは、業界初の「省エネ計算返金保証」を行っております。
個人住宅、小規模事務所から大型工場などまで、幅広く対応しています。まずはお気軽にご相談ください!